2011年03月21日
震災がつなぐ全国ネットワーク

震災がつなぐ全国ネットワーク http://blog.canpan.info/shintsuna/
被災地NGO協働センター( http://www.pure.ne.jp/~ngo/ )の報告です。
http://blog.canpan.info/shintsuna/archive/894#BlogEntryExtend
【東北地方太平洋沖地震】レポート No.15 [2011年03月18日(金)]
被災地NGO協働センターです。
現在、当センターのスタッフ2名は、山形県米沢市で活動しています。
厳しい状況の中で、被災者が避難所の自主運営をしていると、3月18日の朝のニュースに出ていました。被災者のたくましさを感じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新ニュース!
………………………………………………………………………………………
■足湯開始!!
本日午後から市営体育館で「足湯」を行います。
米沢の即席足湯隊が結成されました。
足湯とは、たらいにお湯を張って足をつけてもらい、
被災者の方に心身ともにリラックスしてもらう活動です。
追って報告をお伝えします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
吉椿のレポート
………………………………………………………………………………………
<3月14日>
■ご存じのようにこの地震、津波による被災地は広範囲にわたる。
3月14日、名取の被災地から北上し、南三陸町へと向かった。
現地に向かう道では、警察車両が列をなして、同じ方向へと向かっていた。
ラジオのニュースによるとこの日、南三陸の海岸線に約1000体の遺体が打ち上げられたという。南三陸町の中心地、志津川の手前の小森集落でも津波が襲い、住宅は流され、大型トラックは横転し、田んぼもガレキの海と化していた。たまたますれ違ったお父さんが「あの鉄骨のガレキは、建設会社の建物で元々あそこにあったんだ。」と数百メートル先を指さして教えてくれた。1キロ以上先から流されて来た屋根もあるという。おじさんは、「ここでも6人が未だ行方不明だ」といい残して去って行った。
津波に襲われ、家屋内にガレキが侵入したが、かろうじて流されずに残った家屋に人影を見つけた。近づいて見ると、一人の女性がガレキの中で何かを探していた。
「お母さん、何しているの?」と訊ねると、「靴を探しているのよ。」と返って来た。
「おじいちゃんが自宅の中で亡くなったんだけど、遺体は人にだしてもらったんだよ。」
とぼそりと答えた。その後もひたすら靴を探すお母さん。何かをしていないと気が休まらないのかもしれない。
■南三陸町志津川は、海抜0メートルに近いところに町の中心があった。一般家屋だけでなく、町役場、病院などの公共施設もすべて流され、「総合防災庁舎」の字が津波でむき出しになった赤い鉄骨の間から見えていた。3月14日現在でも約1万人の行方が分からない。
高台に位置している小・中学校に住民の方々は避難している。高台に上がる途中の家屋も傾き、ガレキに呑まれていた。だが、坂の途中のあるラインを越えると地震前とそのままの状態で家屋が残っている。庭にはガレキのひとつさえない。たった数十センチの差でこうも違うのかと思った。坂の上にある志津川小学校のグランドからは津波で廃墟となった志津川
の町が見渡せる。ここには、津波直後、約1000人の住民の方々が避難していたが、現在は約700人ほどに減ったそうだ。過酷な避難所暮らしから逃れるために親戚や友人を頼ってこの地を去って行った。すべてを失くした人達にはこのグランドからの景色はあまりにも酷い。
………………………………………………………………………………………
●東北地方でのボランティア活動資金を募集しています。
●宮崎から東北へ、支援の輪を~「野菜サポーター」を募集しています。
振込口座:郵便振替01180-6-68556
口座名義:被災地NGO恊働センター
通信欄に、「東北地震支援」又は「野菜サポーター」と書いて下さい。
http://www.pure.ne.jp/~ngo/
2011年03月20日
被災地支援、義援金より当座の資金を
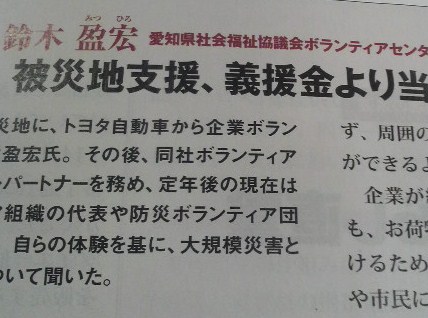
「被災地支援、義援金より当座の資金を」
日経ビジネスより
鈴木盈宏氏の寄稿の一部です。
企業に提案したいのは、ボランティアが現地に入るようになると、そこですぐに使える資金を支援することです。義援金を贈る企業は多く、それは重要です。ですが、義援金は被害の全容が確定するまでは事実上プールされ、後から現地での復興支援に使われるの普通です。そのため被災間もない現場ではボランティアの活動資金が枯渇するというケースが頻発します。義援金と併せて、当面の活動資金を寄付することが、現場のいち早い復興に役立つことを理解してもらいたいと思います。
以上、引用終わりです。
震災がつなぐ全国ネットワークに、注目して下さい。http://blog.canpan.info/shintsuna/
2011年03月20日
震災がつなぐ全国ネットワーク【第9報】

震災がつなぐネットワークの報告です。
http://blog.canpan.info/shintsuna/archive/896#BlogEntryExtend
名古屋のレスキューストックヤードのチームです。
http://rsy-nagoya.com/rsy/
東北地方太平洋沖地震について【第9報】 [2011年03月19日(土)]
みなさま
13日より現地入りしているスタッフ・関口からの現地レポートをお伝えします。
◇3月18日(金)
【気仙沼】
宮城県最北の気仙沼市に入った。個人的なことで恐縮だが、大学時代の研究室がこの地域のまちづくりに参加しており、一度だけだが訪れたことがあった。十数年前のことだ。
そんな思い入れのある気仙沼が、変わり果てていた。
美しい海とユニークな「マグロの貯金箱」などがあった港は見る影もなく、風光明媚な唐桑半島の海岸は防波堤のコンクリートが紙切れのように引きちぎられていた。
そして、自衛隊の空撮映像で赤々とした火に包まれていた鹿折(ししおり)地区。地震、津波、火災に次々と襲われた民家や工場は、あめ細工のように折れ曲がった鉄骨や、黒こげになった骨組みを無残にさらしていた。
まるで爆弾が落ちたような、まさに戦場の様相。
「地獄だ。津波で地獄を見た」
避難所に逃れてから1週間ぶりに戻ってきたというおばあさんは顔をひきつらせて叫んだ。
別の女性は「あそこにいいお肉屋さんが建ってたの。お魚も本当においしかったのよ」と失われた情景を語りながら、呆然と立ち尽くしていた。
ここにはさらに大事な建物があった。社会福祉協議会の事務局が入る福祉センターだ。災害時のボランティアセンターの運営などを担うべき社協の拠点が、跡形もなくなっていた。
社協の機能は被災後、内陸部の老人施設に移ったと聞いた。
訪れると施設の一室にビニールシートが敷かれ、その上に長机やいすが並べられていた。
職員は2人が安否不明。残った職員ががれきの下からパソコンを見つけ出し、ようやく起動できたのがつい今朝のことだったという。
「県社協ともうまく連絡がとりあえず、何から手を付けたらいいかわからない。途方に暮れている」。常務理事の一人は嘆いた。
こうした社協に代わり、市が役所の一画でボランティアの受け付けを始めていた。この日までに市民65人が登録し、一部は物資の仕分けなどを任されている。
火災現場のがれきの片付けなどは危険すぎてボランティアでは担えない。
避難所の支援なら始めやすいはずだが、市内には99カ所の避難所に約2万人が身を寄せており、その数は日々増えている。 今の体制ではとてもボランティアを割り振れないと、嘆く職員の姿がまたあった。
1800人余りの避難所となっている市内の総合体育館では、おにぎり1個で1日2食か3食という被災者の生活が1週間続いている。しかしそれでも恵まれているほうだと、いったん家に戻った住民が再び避難所に集まってくる。
食料、物資不足に加えて、かぜも流行り始めているそうだ。
避難所の責任者は「マスクはいくらあってもいい。全員につけさせたい。
魚のまちだから、町中に散乱した魚がいずれ腐り始めるだろう」と、衛生面を懸念。被災者からも「トイレが詰まってきた。お風呂も入りたい」という声があがっていた。
※ボランティア活動支援金にご協力ください!
・郵便振替00800-3-126026
加入者:特定非営利活動法人レスキューストックヤード
通信欄に「東北地方地震」とご記入ください。
2011年03月19日
喜びへのパスポート(岩手のブログより)
岩手の方のブログです。 http://costyle.e-iwate.com/e2574.html
その一部です。
手をこまねいている暇はない。
ここで僕の言葉を聞いた人達全員に出来ることがある。
皆で動かなければ、沿岸の被災者を救うことは出来ない。
動くことは偽善じゃない。心だけで動かないことが偽善なんだ。
その力を諦めないでほしい。その想いを仕舞い込まないでほしい。
たった一人の声が、大きなムーブメントを作る。
イズムだって、ファッションだって、賛同する誰かを得れば良いだけなんだ。
今日、先輩部員が言った言葉。
YESは数%でも良い。分母を広げることが大事なんだ。
その通りだと思う。僕達がもっと早く動けば、トラック3台分の灯油が運べたかも知れない。
僕達は今日、分母を稼げなかった。
でも来週はもっと分母を稼げるはずだ。そうすれば、また希望を届けられる。
君だって出来る。貴方にだって出来る。
家族で良い、友達で良い、恋人で良い。その想いを打ち明けてみて欲しい。
きっと、やろう!!そう言ってくれる人がいる。
もし、それも駄目なら僕の仲間になってほしい。僕が君の、君が僕の分母になれば良い。
一人じゃ出来ないことをする。そのための仲間だ。そのための種族だ。
僕達は、100年後も、1000年後も日本人だ。
日本の未来を僕達の手で掴み取るんだ。
何度でも言う。
未来は、悲しみの終わる場所だ。喜びへのパスポートを僕達の手に掴もう。
君の力が明日の光に昇華して行くんだから。
2011年03月19日
被災地のブログ
写真は、被災地に、灯油を運ぶボランティアの方のブログです。
http://costyle.e-iwate.com/e2574.html
頑張って下さい。
被災地のブログ集があります。
岩手「いーわブログ」 http://e-iwate.com/
仙台宮城「だてブログ」 http://blog.da-te.jp/
福島「365ブログ」 http://365blog.jp/
2011年03月19日
東日本大震災関連 Twitterタグ一覧(改訂版)

東日本大震災関連 Twitterタグ一覧(改訂版) http://nozbe.com/p/k61t
PublicNozbeプロジェクト(協力:NPO法人AIP)
http://www.facebook.com/publicnozbe
このプロジェクトは、東日本大地震に関する情報収集と発信を行っています。
参加方法 http://www.publicnozbe.jp/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E6%96%B9%E6%B3%95/
2011年03月18日
PublicNozbeプロジェクト(協力:NPO法人AIP)

PublicNozbeプロジェクト(協力:NPO法人AIP)
http://www.facebook.com/publicnozbe
このプロジェクトは、東日本大地震に関する情報収集と発信を行っています。
参加方法 http://www.publicnozbe.jp/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E6%96%B9%E6%B3%95/
2011年03月18日
東北関東大震災【避難所Facebookページ】ボランティア

以下、facebook からの引用です。
東北関東大震災【避難所Facebookページ】構築プロジェクト =ボランティア募集=
2000余の避難所、40万人余、皆さんの辛苦の長期化を憂い、何か援助をしたいと世界中の多くの方が考えていらっしゃると思います。プロジェクト構築のきっかけも同じ思いを持つ仲間の提案からです。
日本の避難所の管理は、県と自治体にまかされているようですが、この状況の中では、自治体の管理とテレビ/ラジオ/伝言ダイアルで伝わる現場の情報が非常に限られたものとなり、避難者とご家族、避難者と支援者を繋ぐ情報の架け橋が、強く求められているものと推察します。
その情報収集と発信の目的に今ベストなツールは、顔の見える個人が、責任を持って情報を発信できるFacebookであるとプロジェクトチームは考え、とにかく力づくで、”全部の避難所のページを作れないか””近くに住むボランティアスタッフが、避難所に行って声を聞き、写真を撮り、Facebookでその声を広く伝えることができないか””避難所単位でその様子や声を確実に伝えることができないか”というプロジェクトを立ち上げました。
<ボランティア募集>
(1)Facebook ファンページの作成/ネット情報収集のできる方
(2)お近くの避難所に行ってFacebookに現地情報を入力できる方
のボランティアを募集します。
(*)(1)は一人で複数の避難所のページ作成も可能かと思いますが、
(2)は、まずは1避難所1人かと思っています。また、(1)(2)を1避難所で兼務もあり得るかと思います。
参照:避難所リスト(3/16日版)
http://dl.dropbox.com/u/12198405/HINANJOLIST0318.pdf
※訪問可能な避難所の番号と名称をご連絡ください。
Facebookページの例
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_205958772764588&ap=1#!/pages/%E9%81%BF%E9%9B%A3%E6%89%80%E6%9D%B1%E6%9D%BE%E5%B3%B6%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B5%A4%E4%BA%95%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C/149308625131376
ご協力いただける方は、このメッセージに、コメントください。メッセージで直接ご連絡をさせていただきます。
2011年03月17日
震災がつなぐ全国ネットワーク

震災がつなぐ全国ネットワーク
http://blog.canpan.info/shintsuna/
新燃岳にも、ボランティアを派遣されました。
第7報です。http://blog.canpan.info/shintsuna/archive/889#BlogEntryExtend
皆さま
13日より現地入りしているスタッフ・関口からの現地レポートをお伝えします。
◇3月16日(水)
【登米(とめ)市】
宮城県北部の登米(とめ)市へ。2005年に9町が合併して人口約8万人、面積約500平方メートルの広さとなった自治体。
人口の半数以上が不明となっている南三陸町に隣接し、内陸側なので被害は少ないと思われていた。しかし、「住民が孤立して社協が混乱している」との情報もあり、物資運びの手伝いを兼ねて現状を確認しにいった。
登米合同庁舎(宮城県の出先機関)では九州からの10tトラック2台が着き、職員の手で物資が次々と下ろされていた。荷物には水やカップ麺、ミルクや毛布などと書いた紙が貼り付けてある。
しかし段ボールの大きさはバラバラで、ビニールに包んだだけのものも。運びにくく、職員同士が手渡す途中にポロリと落としてしまう姿が何度も見られた。
前日には山形JCからの物資10tが届いており、夜通し仕分け作業をしたという。担当職員は「善意で送っていただくのはありがたいが、仕分けする現場は大変」と嘆く。典型的な“救援物資による二次災害”のようだが、職員は「今のところわれわれだけで対応できる。自衛隊の物資受け入れ方針も決まったようなのでこれからはスムーズになるのではないか」とも話した。
この物資はあすには宮城県トラック協会のトラック5台に積み直され、登米市内をはじめ気仙沼、南三陸、石巻、東松島、女川の6市町に運ばれる。県の合同庁舎は気仙沼や石巻にもあるが津波被害で機能できず、登米庁舎が物資の中継基地となっている。その分、物資が集中しているため職員が翻弄されている状態だが、それだけ重要な中継拠点だとも言える。
一方、登米市内の物資輸送は旧町ごとに、水や食料は中田支所へ、紙オムツは南方支所へ、などと役割分担されている。このため流通や情報連絡が複雑となっており、必ずしも効率的な対応とは言いがたい。
迫(はさま)支所近くの体育館では500人以上が避難生活を送っていた。
水や食料は不足気味だが、炊き出しで1日3食が提供できているという。
町名の通り、「米や野菜は十分あります」と避難所の職員。
電気もきょうまでに迫地区で9割ほど復旧しており、家屋被害の少ない登米市民が自宅に戻る日もそう遠くなくなっている。
ただし、登米には津波で壊滅状態の南三陸町から300人ほどが避難している。
南三陸の人たちは帰るところがなく、このまま登米にとどまることになるかもしれない。長期的に登米職員だけで対応ができるとは考えにくい。
登米の避難所に一人で布団に入っていたお年寄りは、気仙沼の親戚一族とまったく連絡がとれないと悲しみに暮れていた。「ほしいものなんて何もない。こうして生きていられるだけでいい」というが、布団のわきには何種類もの持病の薬がある。かかりつけの登米市の病院は開院しているというと「あすには病院に行ってみようかしら」と少し気を取り戻した。
山形のボランティア支援本部では、登米の物流体制や避難所を支援しつつ、被害の大きい気仙沼や石巻へも支援の手を伸ばす拠点にできないか、と提案する声もある。
あす以降、実際に登米から気仙沼、石巻に入って状況を調べる予定。
※本日より「東北地方太平洋沖地震ボランティア活動支援募金」開始!ご協力頂ける方はRSY事務所までご一報ください。
3月17日(木)16:30~18:30
18日(金)16:30~18:30
19日(土)14:00~17:00
20日(日)14:00~17:00
・場所:名古屋市栄三越ライオン前周辺
※ボランティア活動支援金にご協力ください!
・郵便振替00800-3-126026
加入者:特定非営利活動法人レスキューストックヤード
通信欄に「東北地方地震」とご記入ください。
2011年03月17日
中越発 救援物資はもういらない!?

あなたの善意をどう届けるか? 「中越発 救援物資はもういらない!?〜新しい善意(マゴコロ)の届け方」から災害支援を考える
http://kachi-labo.com/diary/2168
「災害時における一方的な善意(利己的なボランティアや不特定多数への救援物資)が、被災地に対して第二の災害を引き起こす」
詳しくは上記のブログを読みましょう。
2011年03月17日
避難所名簿を撮影した写真を公開!Google

避難所名簿を撮影した写真を公開!Google 避難所名簿共有サービス
ライブドアの記事 http://news.livedoor.com/article/detail/5418118/
実際の写真 https://picasaweb.google.com/116505943227607394790/2011_03_14_1300_name_list#
身内の方の情報を求めて、避難場所を、何カ所も尋ね歩く被災者が多数おられるようです。



