2017年06月20日
塩村文夏さんが見た都議会「職員ともたれ合いの構造」 波瀾万丈の4年を振り返る【都議選2017】

【地方?議会問題】
福岡市役所の今村寛さんのタイムラインからです。
以下、今村さんの投稿です。
都議会の「伏魔殿」っぷり,すごいですね^_^;
これが真実なのかどうか,ご本人の言い分だけですので,反論したい方もおられるのだとは思いますが,東京都民がこのことをどう受け止めているのか,知りたいもんです。
私の知る限り,福岡市議会ではこんなことないよなーと思いながら読みましたが,ほかの地方自治体の皆さん,地方議会の皆さん,いかがお感じですかね(^_-)-☆
http://www.huffingtonpost.jp/2017/06/15/ayaka-shiomura-and-metropolitan-assembly_n_17111108.html
塩村文夏さんが見た都議会「職員ともたれ合いの構造」 波瀾万丈の4年を振り返る【都議選2017】
東京都議選が6月23日に告示され、7月2日に投開票される。
この4年間はおそらく、かつてない注目が都議会や都政に集まった時期だった。猪瀬直樹・元知事が「政治と金」を巡る問題で辞職。続く舛添要一氏もやはり「政治と金」が問題視され知事の職を辞した。4年で3人目の知事となった小池百合子知事は、懸案だった豊洲市場移転をどう決断するのか注目が集まる。
都議会のあり方も大きく問われた。2016年、リオ・オリンピックへの都議の出張は、そのあり方が大きく批判され中止に追い込まれた。2014年には晩婚化対策を質問していた塩村文夏都議に「お前が早く結婚すればいいじゃないか」「産めないのか」というやじが飛び、大きな批判を浴びた。
都議会が注目されるきっかけになった塩村都議は、国政に転身するため次期都議選には出馬しない。放送作家やタレントといった政治と縁遠い世界から飛び込んだ都庁、そして都議会はどんな世界だったのか。4年間を振り返ってもらった。
■少数会派はつらいよ
——4年間つとめてこられて、立候補前に思っていた都議の仕事と印象はどう変わりましたか? 思っていたこととどんなことが違いましたか。
年配の男性が多くて縦社会というのは本当でした。「政治は古い人がやっていて、分かっていないから、古い慣行がまかりとおっている」というのは確かなんだけれども、新しい意見でいいものでも、頑固に取り入れないんです。自分たちが主導権を握っているんだぞという人たちで占められていたのが現実で、提案なんかできる雰囲気もないし、議場と言っても、議論にならない。都民の代表というよりは、どちらかと言うと行政側に近いような印象があります。
——旧みんなの党公認で当選して、現在は一人会派。ずっと少数会派だったので、数の面で苦労されたということでしょうか。それとも、そういうものを超えた議論のしにくさがあったのでしょうか。
数がパワーというのは本当でした。だから何を言っても通じないですし、行政側も数を見ながら対応しますから、こっちを向いてないですよね。知事の予算要望も複数会派以上じゃないと聞いてもらえない。世田谷区で私より下位当選した会派の予算要望は受けつけられていますから、理由をつけて断られる。議会改革を話し合う「在り方検討会」にも入れてもらえないし、何を話したのかも知らされない。都議会広報には一般質問の顔写真が一人会派の議員は載らない。一人会派は議員じゃないという雰囲気は議会でも、行政側からも感じました。
——放送作家などの活動をしながら、政治に遠い世界から飛び込みました。
議員になる前は放送作家としてメインでテレビを、そしてラジオ番組も担当していました。東京に憧れて東京に出てきて働く女性で、ようやく仕事も非正規とはいえ何となく安定してきた。なのに子供を産もうと思っても産めないじゃん。休んだら収入も途絶えちゃう。うまく子供を産めたとしても待機児童になっちゃう。キャリア積めないじゃん、どうしたらいいんだというジレンマにぶち当たった。
それから動物愛護の問題。国政でも区議選でもなく都議選に出たのは、動物愛護センターの行政官管轄が広域自治体の東京「都」にあったからです。
議員になる前は、いい提案をすれば気づかなかった人たちが「これいいね、やろう」となると思っていたけど、そうならないと気付いた。何回もめげました。認めないですから、何を言っても。行政側の答弁のロジックがおかしいときには、根拠となるものを全部見つけだして、現地に足を運んで写真を撮る。その作業に夜中まで、時には朝までかかる。その繰り返しでしたね。
与党の先生が、質問調整をささっと終えて帰られるのを見ると、私がやっていることは理解できないんだろうなあと思いますよね。
一人会派は訴えたいことを思う存分、一般質問の持ち時間やブログで発信することはできますが、施策に反映させるのがすごく難しい。提案しても、私が望むような回答が私の質問のときには出てこず、次の与党の質問で「やります、改善します」と答える、みたいなことが続いていく。かつては悪くない答弁も頂けていたんですが、ある日、大会派の先生が職員に「おい、ずいぶんサービスいいじゃないか」と委員会で言ったら、その瞬間に職員の顔が青ざめたんです。それを見た瞬間「あっ」と思いました。
ただ、やっていくうちに、少数会派の役割がわかってきました。だれも取り上げなければ改善されなかったことを、しっかり都議会で訴え、議事録に残すことで、行政側も動かざるを得なくなる。自分の仕事は、いいことを提案して「私はこれを変えました」と誇るんじゃなくて、おかしいことを東京都に認識して変えてもらうことだな、それが与野党の違いとすごく認識させられた。
だから途中から、おかしいことを徹底的におかしいと追及する戦法に変えたら、動物愛護や待機児童問題でもこの4年で大きく変わった。私が当選した時はまだまだ都の重要課題ではなかったですから、やっぱり続けていくのは重要だと思っています。
——自分の質問で変わったことはありましたか。
待機児童の問題で、建物の検査済証がなかったり紛失していたりする建物を、安全が確認できれば保育施設に使ってもいいように通達してくれと、世田谷区長が知事との懇談の中で提案して、私も一般質問を通告したんです。
通告から質問まで3日ぐらいあるんですが、当初は「わかってるんだけどね、春ぐらいまでには」という回答だったのが、質問を通告したとたんに「今日の6時までに通達を出しますから、この質問、意味がなくなります」と言ってきた。野党の先生に花を持たせたことになるから、質問前までに実施する。野党も使い方だなと思いました。
動物愛護センターの改修も、当選直後の最初の委員会の質問から、私が何回も言いつづけてきました。それを多くのSNSフォロワーが拡散をして応援してくれて、他の議員もそこで気付くんです「確かに愛護センターぼろいぞ」って。いきなり動物愛護の機運が高まってきて、急にいろんな議員さんから質問が出て、ついに愛護センターの建て替えが決まりました。私が言ったことで変わったわけではないけれど、言い続けたことで取りあげられ始めたんですよね。
花は持たせてもらえないけど、改善まで持っていくのが仕事。まあ、でもいつかは「私が言ったことで変わりました」というのも、言ってみたいことのひとつではあるから、みんな与党になりたがるのもわからないではないけれど。
■なあなあな都議会、都政との癒着
——都庁は伏魔殿だと言われます。議員として向き合ってみた東京都庁という組織は手強いところでしたか?
ピラミッド形で、上を見ている組織。何をするにしてもその場で返事せず、上にお伺いを立てに戻っていくんですよ。自分で責任を負いたくない。時間がかかってしょうがない。都民の方を向いていないと感じることが多々ありました。
職員の評価が減点主義なんでしょうね。追及されたら斜め45度から強引な理屈をこねる。私が議会で「これはおかしい」と追及すると、「これまではこうやってきた、今はこれをやっている、今後ともこうしていく」という言い方をして、改善もしないし認めない。でも後からこそっと変えていることもある。追及を続けていると職員に嫌われるし、次も絶対にいい回答をもらえないので、議員はなかなか言えなくなる。
逆に大会派を敵に回すと、行政側の予算も認めてもらえませんから、いいことを提案させて「先生の提案でやります」と答弁する。その代わりに悪いところはあまり追及させない。最終的に改善されればいいんだけども、議会としても不健全です。
東京都の施策って、全部平均的に高得点の優等生なものが多い気がします。失敗は絶対してはいけないのだと。お金をかけているから進んでいるように見えるし、何かをやると決めたときは良くも悪くも強いんだけれど、総じてオリンピックを除くと、まったくアイデアから全国初というより全国で早期に始めましたという方が多い印象です。
——びっくりしたことってありましたか?
海外視察ですかね。あってもいいと思うんですよ、世界の首都の東京ですから。しかし何かにつけて議連を作って海外視察。それも毎回ドント方式で割りますから、絶対に一人会派に回ってこない。同じ会派の人たちばかりでもたれ合ってるのを感じます。
——リオ・オリンピックでは問題に大きな批判を浴びました。
あれは変でしたよ。舛添知事の問題があって「理解が得られない」と辞退した会派の分を、大会派で割り振り直す悪質なものでした。あの状況で私に声がかかっても行かなかったと思いますけれども、セコさというか浅ましさが見えましたね。
——他には?
一度、会派控室で金銭の出納帳がなくなって、Facebookなどで騒いでいたら、ある日いきなり戻ってきたことがありました。議会局に「防犯カメラの映像を見せてくれ」と言ったら、職員が「見たんですけど怪しいものは何も写っていません」と言ってきた。
「部長の命令で、『怪しいものは一切写っていなかった』と言ってこいと言われて僕は来ています」
「あなたの言う『怪しい』の定義って何?」
「僕たちの言う『怪しい』の定義とは、唐草模様のほおかむりをしている人です」
「いるわけないだろ!」
見せろ、見せないのやりとりの後、新宿署に連絡して、警視庁から要望を書面で出したら、防犯カメラの記録動画を出してきたんだそうですが、帳簿がなくなった日は「最初から写っていなかった」と言い出して、返ってきた日は映像が別の場所にすり替わっていました。正しい画像を提出するよう警視庁が要望すると「すべてもう消去しました」と都の議会局は返答してきました。
今は笑い話のように話していますけど、胃が痛くなるんですよ。平等ですらないし、公平にすら戦えない。私はメンタルが鋼鉄だと言われていますけど、2回ぐらい泣いたことがあるんです。普通の女性でどれだけ耐えられるか。
——都議会でやり残したことは?
やはり議会改革ですよね。ある種、職員も含めてもたれ合っていると思うんです。職員も大会派の先生の意向をくんでおけば、安泰じゃないですか。
海外視察もそうですし、費用弁償はなくなりましたけれども全国最高の1日1万円だったし、政務活動費も全国最高の月60万円が50万円になりましたけれども、これだけの特典がついているんだから「お互いうまくやりましょう」というところがあると思うんですよね。私たちが適正な要求と行動をしていれば、もっと職員たちに「おかしい」と言えるんだけど、もたれあっちゃってるもんだから、なかなか。
一人ひとりが都民の代表だという自覚を持ってきちんと仕事をすることが、振る舞いも含めて重要なんですけども、なんかね「選ばれし者」になってますから。選ばれたという意味を履き違えている人が多い。やっぱりその体質が見られていないからで、猪瀬元知事の言葉を借りればどんどん「光を当てる」ことで、一人ひとりが真っ当な議員として行動ができる環境作りは必要だと思っていました。
——時代と共に改まっていくという感じでもないようですね。
やっぱり注目されていないとダメですよ。私のヤジの問題や舛添前知事の前は、都政や都議会なんてほとんど注目されていませんでしたから。いくら志の高い議員でも、本当に強い思いを持っていないと、シメシメと流されちゃうんですよ。いろんな人が見るようになれば、隠したいことがどんどん外に出ていく。だから報道してもらえることってすごい重要だと思っているし、政治を監視というか、注目することは重要なんです。
後編はこちら⇒
「セクハラやじ」から3年、都議会や女性議員のあり方は変わったか 塩村文夏さんに聞く【都議選2017】
http://www.huffingtonpost.jp/2017/06/16/ayaka-shiomura-and-sexual-harassment-hooting_n_17145644.html
しおむら・あやか 1978年生まれ、広島県出身。タレントや放送作家などを経て、2013年の都議選で世田谷区選挙区から旧みんなの党公認で初当選。現在は一人会派「東京みんなの改革」所属。次期衆院選に民進党公認で立候補することが決まっており、今回の都議選には出馬しない。
2017年06月10日
市民と議員の条例づくり交流会議2017 「議会のチェック機能を本気で考える」
【東京での勉強会など】

【市民と議員の条例づくり交流会議2017
「議会のチェック機能を本気で考える」】
7月29日(土)、30日(日)、法政大学市ヶ谷キャンパスです。
https://www.facebook.com/events/108406416431090/
以下、facebook のイベントからです。
市民と議員の条例づくり交流会議2017(第17回)
議会改革の新たな視点 議会のチェック機能を本気で考える
議選監査委員を再考する、新公会計制度と決算審査、シチズンシップ教育と議会、議会基本条例を改めて学ぶ、ほか
日時:2017年7月29日(土)-30日(日)
会場:法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎
参加費:議員1万円、市民2千円
(※要申し込み:しばしお待ち下さい)
平成29年の通常国会(第193回国会)で地方自治法等の一部を改正する法律が可決され、監査制度の充実強化のために、条例により議会から選出される監査委員をなくし、外部の監査専門委員の創設が可能となりました。また、今回の改正では、議会が決算を不認定にした場合に首長が行った措置を議会に報告することも定められました。
法律の施行は、平成 32 年からです。それまでに、議選監査委員は必要なのか、機能しているかの再考が求められることになります。さらに、現在の決算審査のままで良いのかも問われることになります。
決算審議の前に、あらためて議選監査委員の意義を考え、議会の重要な機能であるチェック機能が果たせているのか、今のままで良いのか。新たな議会改革として議論します。どうぞ、ご参加ください!

【市民と議員の条例づくり交流会議2017
「議会のチェック機能を本気で考える」】
7月29日(土)、30日(日)、法政大学市ヶ谷キャンパスです。
https://www.facebook.com/events/108406416431090/
以下、facebook のイベントからです。
市民と議員の条例づくり交流会議2017(第17回)
議会改革の新たな視点 議会のチェック機能を本気で考える
議選監査委員を再考する、新公会計制度と決算審査、シチズンシップ教育と議会、議会基本条例を改めて学ぶ、ほか
日時:2017年7月29日(土)-30日(日)
会場:法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎
参加費:議員1万円、市民2千円
(※要申し込み:しばしお待ち下さい)
平成29年の通常国会(第193回国会)で地方自治法等の一部を改正する法律が可決され、監査制度の充実強化のために、条例により議会から選出される監査委員をなくし、外部の監査専門委員の創設が可能となりました。また、今回の改正では、議会が決算を不認定にした場合に首長が行った措置を議会に報告することも定められました。
法律の施行は、平成 32 年からです。それまでに、議選監査委員は必要なのか、機能しているかの再考が求められることになります。さらに、現在の決算審査のままで良いのかも問われることになります。
決算審議の前に、あらためて議選監査委員の意義を考え、議会の重要な機能であるチェック機能が果たせているのか、今のままで良いのか。新たな議会改革として議論します。どうぞ、ご参加ください!
2017年02月16日
議会基本条例10年シンポジウム「九州から問う 議会改革」
https://www.tkfd.or.jp/research/local-assembly/18667i
議会基本条例10年シンポジウム「九州から問う 議会改革」
日時2017/3/11 14:00-16:30(開場 13:30)
場所福岡ビル 9階大ホール(福岡市中央区天神1丁目11番17号)
定員100名
参加参加費無料、要事前登録。定員に達し次第、受付を閉め切ります
北海道の栗山町議会が全国に先駆けて議会基本条例を制定してから10年。今では800近くの議会で基本条例が施行され、議会のあり方が明確になってきましたが、議会と市民の関係、議会と首長(行政)の関係はどう変化したのでしょうか。また、議員間の討議はすすんでいるのでしょうか。
九州最大の都市・福岡で開催するシンポジウムでは、東京財団が議会基本条例の必須要件と定める「議会報告会、意見交換会」「議会への市民参加」「議員間の自由討議」を軸に、基本条例の原点とその意義をあらためて確認し、この10年の議会の歩みを検証します。さらには、人口減少社会における議会の役割や課題を踏まえつつ、具体的な事例を交えて議会改革の今後を展望します。お誘い合わせの上、ご参加ください。
パネリスト:
千葉茂明 月刊『ガバナンス』編集長 (※コーディネーター)
中尾 修 東京財団研究員、元北海道栗山町議会事務局長
廣瀬克哉 法政大学法学部政治学科教授
前田隆夫 西日本新聞報道センター部次長
総合司会:
吉村慎一 議会事務局研究会
プログラム:
14:00-15:20パネリスト/コーディネーターの報告
15:20-15:30休憩(質問票の回収)
15:30-16:30パネル討論(含質問への回答)
東京財団主催、西日本新聞社共催
- See more at: https://www.tkfd.or.jp/research/local-assembly/18667i#sthash.ngH3HzbY.dpuf
議会基本条例10年シンポジウム「九州から問う 議会改革」
日時2017/3/11 14:00-16:30(開場 13:30)
場所福岡ビル 9階大ホール(福岡市中央区天神1丁目11番17号)
定員100名
参加参加費無料、要事前登録。定員に達し次第、受付を閉め切ります
北海道の栗山町議会が全国に先駆けて議会基本条例を制定してから10年。今では800近くの議会で基本条例が施行され、議会のあり方が明確になってきましたが、議会と市民の関係、議会と首長(行政)の関係はどう変化したのでしょうか。また、議員間の討議はすすんでいるのでしょうか。
九州最大の都市・福岡で開催するシンポジウムでは、東京財団が議会基本条例の必須要件と定める「議会報告会、意見交換会」「議会への市民参加」「議員間の自由討議」を軸に、基本条例の原点とその意義をあらためて確認し、この10年の議会の歩みを検証します。さらには、人口減少社会における議会の役割や課題を踏まえつつ、具体的な事例を交えて議会改革の今後を展望します。お誘い合わせの上、ご参加ください。
パネリスト:
千葉茂明 月刊『ガバナンス』編集長 (※コーディネーター)
中尾 修 東京財団研究員、元北海道栗山町議会事務局長
廣瀬克哉 法政大学法学部政治学科教授
前田隆夫 西日本新聞報道センター部次長
総合司会:
吉村慎一 議会事務局研究会
プログラム:
14:00-15:20パネリスト/コーディネーターの報告
15:20-15:30休憩(質問票の回収)
15:30-16:30パネル討論(含質問への回答)
東京財団主催、西日本新聞社共催
- See more at: https://www.tkfd.or.jp/research/local-assembly/18667i#sthash.ngH3HzbY.dpuf
2017年01月18日
市民と議員のdialogue

いいイベントです。
春日市市議会議員、西川文代さん( https://www.facebook.com/profile.php?id=100005384522411 )からです。
https://www.facebook.com/events/1654803108151674/
以下、facebook のイベントからです。
【 福岡女子大学 社会人学び直し大学院 イノベーション創出力を持った女性リーダー育成プログラム×NPO法人『 YouthCreate』とのコラボ開催!】
YouthCreate 原田代表と創る
Voters Bar with みらいcafé in春日
~市民と議員のdialogue〜
<大好きなまち・目指す地域の
『いま』と『これから』を考える>
突然ですが・・・
政治家と直接おしゃべりしてみませんか?
「政治家って正直ちょっと固いイメージ…」
「政治の話題に興味がないわけじゃない。
けど、なんか遠いしよく分からない…」
固くて、遠くて、よく分からない。
その気持ち、よ~くわかります。
でもでも!!
一見とっつきにくそうな政治の中でも、
自分がよく知っている話題なら、なんとなくハードル低く感じませんか?
身近な話題を切り口に、「政治」に触れてみる。
これまで得体の知れなかった「政治」が、一気に身近なものになる!
「みらいcafé」が、
そのきっかけになれば嬉しいです。
こんな方へおススメします!
◆選挙に行ってはいるけれど、よく知らないまま投票してる…
◆政治、と聞いてもなんだかピンとこない…
◆ 議員さんと直接話をしてみたい!
◆まちづくりについて興味があるけどくわしくはわからない・・・。
政治・選挙のことが良くわからなくてもOK!
福岡のこと、春日のこと、
いろんな方とざっくばらんに政治について話してみませんか?
みなさまのご参加お待ちしています♡
=================================
【詳細】
Voters Bar with みらいcafé
~市民と議員のdialogue〜
日時:2017年 1 月 21 日 (土) 13:45~16:50 (予定)
受付スタート 13:25~
場所 クローバープラザ 東棟5F研修室506AB
福岡県春日市原町3丁目1番7号
参加者 福岡県民・春日市民
参加費 社会人 500円 学生 200円
ドリンク代として、各イベント毎に参加費を徴収させていただきます!
★お友達を誘ってご参加いただいた学生さんは1人分無料になります^^
=================================
◆主催・運営団体◆
・春日の未来を考える有志の会
・みらいcafé実行委員会
・職業実践力育成プログラム(BP)認定
福岡女子大学 社会人学び直し大学院
イノベーション創出力を持った 女性リーダー育成プログラム
◆共催◆
<NPO 法人 YouthCreate>
「若者と政治をつなぐ」をコンセプトに活動をしている NPO 法人。
「若者が政治に主体的に関わること」、「若者を社会の担い手の一人とする仕組みづくり」を目指し、
地域の議員と若者がお酒を片手に気軽に語り合うイベント:若者と政治家の気軽な交流会「Voters Bar」を開催している。
◆お問い合わせ◆
職業実践力育成プログラム(BP)認定
福岡女子大学
社会人学び直し大学院プログラム履修生
春日市議会議員
西川文代
leopalace21 solution section
新規事業開発担当 チーフ
滑石 吏紗
*当日は政治的偏りはなく、共に地域社会を創るという、住民仲間意識のスタンスでの対話となります。議員5、6名参加予定です。
タグ :YouthCreate春日の未来を考える有志の会職業実践力育成プログラム社会人学び直し大学院西川文代春日市 西川文代西川文代 春日市滑石 吏紗leopalece21 滑石 吏紗滑石 吏紗 leopalace21
2015年04月12日
立候補は必ず男女二人で 西日本新聞
【立候補は必ず男女二人で 平成27年4月5日 西日本新聞】
フランス全土の県議選では、議員の男女比を同じにするために男女2人一組で立候補するという世界初の制度を導入した。
今回の福岡市議会議員選挙では、早良区、博多区では、女性に立候補者ですら、一人もいなかった。
前回の2011年の選挙で、当選したのは、東区一人、中央区一人、西区二人です。
女性の枠を作っもいいと思います。
タグ :立候補は必ず男女二人で立候補は必ず男女二人で フランスフランス 立候補は必ず男女二人でフランス県議会 立候補は必ず男女二人で立候補は必ず男女二人で フランス県議会フランス県議会福岡市を世界一魅力ある街に福岡市 世界一魅力世界一魅力 福岡市福岡 世界一魅力
2015年03月24日
地方議会の女性議員12%にとどまる
facebook で注目している中のお一人、今井淑子さんの投稿からです。
以下、今井さんの投稿です。
◆地方議会の女性議員 約12%にとどまる◆
▽都道府県議会議員8.9%
▽市議会と区議会議員13.8%
▽町村議会議員8.9%
・日本全体に“政治は男性の領域”という意識の壁
・家族や親族の反対の壁
・現職でいる男性議員が女性の参入を許さない壁
・議会のシステムそのものの壁
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150321/k10010023691000.html
また、日本経済新聞からです。
日本経済新聞 3月23日
慶応大学法学部教授
片山善博氏
「地方創世の課題は市域に若者や女性がいなくなる点が挙げられるが、議会がそういった人々からそっぽを向かれている。女性議員がいないどころか、立候補すらないところもある。そんな状況で他の地域に人が流出するのは当たり前だ。」
「通年議会を導入し、毎週水曜など定例日の夕方から審議すれば、仕事帰りの会社員なども議会に参画しやすくなる。請願を出した住民が趣旨を議会で説明できるようにし、審議の過程で住民の意思が反映できるようにすれば、議会への関心も高まる。決まったことを説明する議会報告会よりもいい。私なら、候補者にそういう事をしますかと問いたい。」
以下、今井さんの投稿です。
◆地方議会の女性議員 約12%にとどまる◆
▽都道府県議会議員8.9%
▽市議会と区議会議員13.8%
▽町村議会議員8.9%
・日本全体に“政治は男性の領域”という意識の壁
・家族や親族の反対の壁
・現職でいる男性議員が女性の参入を許さない壁
・議会のシステムそのものの壁
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150321/k10010023691000.html
また、日本経済新聞からです。
日本経済新聞 3月23日
慶応大学法学部教授
片山善博氏
「地方創世の課題は市域に若者や女性がいなくなる点が挙げられるが、議会がそういった人々からそっぽを向かれている。女性議員がいないどころか、立候補すらないところもある。そんな状況で他の地域に人が流出するのは当たり前だ。」
「通年議会を導入し、毎週水曜など定例日の夕方から審議すれば、仕事帰りの会社員なども議会に参画しやすくなる。請願を出した住民が趣旨を議会で説明できるようにし、審議の過程で住民の意思が反映できるようにすれば、議会への関心も高まる。決まったことを説明する議会報告会よりもいい。私なら、候補者にそういう事をしますかと問いたい。」
2014年10月08日
市民と議会の条例づくり交流会議in九州

見てるか?議会 【市民と議会の条例づくり交流会議in九州】
http://jkyushu.com/
来週の月曜日、10月13日、午後1時から、福岡市のガスホールであります。
私も、参加予定です。
facebook イベント https://www.facebook.com/#!/events/451754071633971/?ref_dashboard_filter=calendar&source=1
2014年08月17日
地方議員の口利き

地方議会に関心持とう 片山善博氏
平成26年8月15日 西日本新聞夕刊より
(前略)
コツコツと真面目に仕事をしている議員も少なからずいる。その上で長年地方議会をウォッチしてきた筆者の印象をあえて言えば、個々の議員だけでなく、地方議会自体もあまり評判はよくない。住民の中には議会に対する諦めや不信感さえみてとれる。
その原因の一つに「口利き」がある。口利きとは、議員が支持者などからの頼まれごとを役所に取り次ぎ、その実現を図る行為をいう。卑近な例を挙げてみる。
昨年、東京都杉並区などで幼児をもつ親が、保育所の待機児童問題が一向に解消しない現状に業を煮やし、行政不服審査法に基づき異議の申し立てを行った。これがきっかけとなって、その後の多くの自治体でこの問題に力を入れるようになったことは記憶に新しい。
その頃、筆者は知り合いの議員に尋ねてみた。待機児童問題がこんなに深刻だというのに、議会はこれまで何をしていたのか、と。それに対して議員は不服そうな表情で即座に答えた。
自分は真剣に取り組んできた。現に昨年も役所に掛け合い、頼まれた子ども3人を保育所に入れた、というのである。その子たちの親や祖父母から随分と感謝されたそうだ。それが有権者の支持をしっかりつなぐことにもなるという。
これが典型的な口利きである。これこそが重要な議員活動だとして熱心に取り組んでいる議員が多いのだが、大いなる思い違いというほかない。
ちょっと考えてみると容易に分かることだが、保育所の定員を増やさないまま議員が1人の子を押し込めば、必然的にどこかの誰かが1人はみ出る。事態は何も解決しないし、そこに不公正が介在しているから、事態はより悪化したと見るべきだ。
うがった見方をすると、口利きが仕事だと勘違いしている議員にとって、本音では待機児童問題は解決しない方がいい。待機児童がいなくなると、口利きを頼みに来る人もいなくなるから、議員にとっては有権者の支持をつなぐ機会を失うことになる。
ひょっとして、これまで問題を解決しなかった背景に、議員のこんなゆがんだ心理があったのではないかと、つい勘繰りたくもなる。
議員たちは本来何をすべきか。それは、支持者から子や孫を保育所に入れてくれと頼まれたら、その子だけではなく他の子どもたちも一緒に入所できるように取り計らうことである。それには保育所の定員を増やすための予算を確保する必要がある。
もし、そのための財源がなければ、予算案を組み替え、優先順位の劣る事業を削ることで捻出したお金を保育に回せばいい。その権限は議会に備わっている。
ほとんどの自治体では首長が出した予算案などの議案をそのまま無傷で通しているのが現状である。
それが自分たちの役目だと思い込んでいる議員が多いが、原案が何も変わらないのなら議会などあってもなくても同じことだ。そうではなくて、住民の意向を踏まえ、議案を是々非々の態度でチェックし、必要なら修正するし、場合によって否決することだってある。
こんな気概と力量をもつ議員であれば、それこそ議場で下品なやじを飛ばしたり政務活動費の使い道に偽装を施したりする暇など毛頭なかろう。
出来の悪い議員を選ぶのも有権者なら、良質の議員を選ぶのも有権者に他ならない。この際、有権者は地方議会にもっと関心を持ち、1人でも多く、良質の議員を選ぶように心掛けたいものだ。
2014年07月27日
市民と議員の条例づくり交流会議2014

市民と議員の条例づくり交流会議2014(第14回)https://www.facebook.com/events/585533571561588/?ref_dashboard_filter=upcoming
に、参加してきました。たくさんの議員の方などと交流ができました。
「情報公開」「議員間の自由討議」「議会報告会の実施」などの議会基本条例を2014年中には地方議会全体の3割(約600議会)で、制定される見込みだそうです。福岡市議会では、検討されているようですが、「結論を得るには至らなかった」とのことです。http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/1353/1/1gikaikasseikanogaiyou.pdf
2014年07月16日
市民と議員の条例づくり交流会議2014
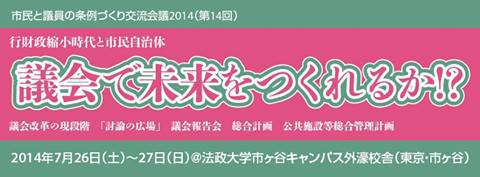
【市民と議員の条例づくり交流会議2014】
7月26日(土)~27日(日)に、東京で開催されるので、一般市民として、参加してきます。
https://www.facebook.com/#!/events/585533571561588/?ref_dashboard_filter=calendar
以下、facebook のイベントからです。
行財政縮小時代と市民自治体
議会で未来をつくれるか!?
議会改革の現段階 「討論の広場」 議会報告会 総合計画 公共施設等総合管理計画
【開催概要】
日時:2014年7月26日(土)14時~17時、27日(日)10時~15時30分
会場:法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎(東京・市ヶ谷)
参加費:市民2,000(会員無料)、議員10,000円(会員5,000円)
(交流会参加費:別途3,000円)
主催:市民と議員の条例づくり交流会議 自治体議会改革フォーラム
共催:法政大学ボアソナード記念現代法研究所
要申込:7月11日(金)〆切
【プログラム案(2014年6月12日現在)】
>>>>>>>>>>
第1日 7月26日(土)全体会
>>>>>>>>>>
13時00分 開場・受付開始
14時00分 開会
14時10分 全体会
議会改革の現段階(2014調査報告)
長野基(首都大学東京)
14時30分 全体会
行財政縮小時代に地域の未来をどうつくる!?
自治体の将来ビジョンをどのように選び、実現していくのか
基調提起「議会はこの課題を担えるか」
廣瀬克哉(自治体議会改革フォーラム)
パネルディスカッション
神原勝(北海学園大学教授)
「自律自治体の構築と自治基本条例・議会基本条例・総合計画条例」
神吉信之(ローカル・マニフェスト推進ネットワーク九州・代表)
「選挙とマニフェスト型自治体運営」
中尾修(東京財団研究員)
17時00分 第1日・全体会・終了
18時00分 交流会(~19時30分)
>>>>>>>>>>
第2日 7月27日(日)全体会&グループセッション
>>>>>>>>>>
09時30分 開場
10時00分
公共施設等総合管理計画
縮小時代の未来を市民・議会・行政でどうつくる?
基調提起:菅原敏夫(公益財団法人地方自治総合研究所)
パネルディスカッション
本川祐治郎(富山県氷見市長)
「新しい公共施設・利活用のカタチ―デザインワークショップで学校体育館を新市庁舎へ」
藤縄善朗(埼玉県鶴ヶ島市長)=NEW=
饗庭伸(首都大学東京准教授)
「都市をたたむ技術/参加と納得の合意形成のための手法」
コーディネーター:廣瀬克哉(自治体議会改革フォーラム)
12時00分 お昼休み
13時00分 テーマごとのグループセッション
テーマA
「どうする!?議員間討議」
テーマB
「やってよかった!議会報告会×いってよかった!議会報告会」
テーマC
「どうする!?わがまちの公共施設等総合管理計画」
15時00分 グループセッション全体共有
15時30分 第2日・終了
2014年06月29日
変えよう地方議会―3・11後の自治に向けて
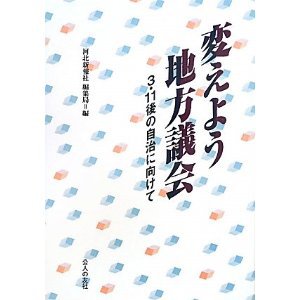
【変えよう地方議会―3・11後の自治に向けて】 河北新報社編集 公人の友社
「住民との意見交換会の開催」に「議員間の自由討議」と「請願は住民からの政策提言」を加えて改革議会の必須3要件とあります。
北海道栗山町議会と福島県会津若松市議会が議会改革が進んでいるので、機会があれば、会津若松市議会に行ってみようと思います。
2014年06月28日
未来を大切にする市議&候補者合宿

7月12日(土)から13日(日)に、「未来を大切にする市議&候補者合宿」( http://harada-sunaga.com/news )に参加してきます。
地方から日本の未来を変えるための本気の作戦会議です。
糸島市議会議員の藤井芳広さんのfacebook のタイムラインから、知りました。新しい政治の流れのような気がしています。
2011年03月08日
福岡の経済活性化などをめぐり新人たちが熱い討論

先日、公開討論会に参加してきました。
データマッスのネットアイビーの記事です。
http://www.data-max.co.jp/2011/03/post_13962.html
新人同士の討論会で、大変勉強になりました。
福岡市の経済の浮揚に関しては、喫緊の課題であると考えています。
お世話いただいた皆様、ありがとうございました。
2011年02月18日
市民と議員の条例づくり交流会議in関西

「交流会議in関西/2/20@大阪府茨木市―議会は何をするところ?関西発!みえる議会わかる議会いかす議会」
http://kouriu-kansai.jimdo.com/
―申込〆切は2/18(金)10時。準備の関係上、早めのお申し込みを!http://bit.ly/hmN1iM#cgtf
主催
自治体議会改革フォーラム http://www.gikai-kaikaku.net/
市民と議員の条例づくり交流会議 http://www.citizens-i.org/jourei/
2011年02月11日
名古屋ショック・二元代表制はゆらぐか

2月9日の西日本新聞の特集です。
タイトル 名古屋ショック・地域政党と民意
サブタイトル 警戒 二元代表制は揺らぐか
以下、引用です。
首長と議会。選挙で選ばれた両者が互いにけん制しあう二元代表制は地方自治の原則だ。「首長新党」は二元代表制を脅かす存在にならないか。
(中略)
「大阪維新の会」や「減税日本」を勢いづかせている最大の要因は、代表を務める橋下、河村の個人的な人気だ。
以上引用終わりです。
二元代表制そのものに対する議論は別として、福岡市などの、市役所と市議会が、ほとんど一体化していることに、市民は、憤りを感じています。
議会が、福岡市政に、国民、市民のためのチェック機能が、できていれば、「議会はいらない」という市民の声は出ないと思います。
2011年02月09日
「名古屋ショック」地域政党と民意・西日本

昨日の西日本新聞の1面の特集です。
タイトル 「名古屋ショック」地域政党と民意
サブタイトル 不満・既成政党と議会 敵役に
中身から抜粋します。
圧勝だった。民主党推薦候補にトリプルスコア以上の大差をつけた市長選の得票数は過去最多。愛知県知事選でも盟友の前衆議院議員大村秀明氏が、民主、自民両党支援候補を圧倒し、市議解散を問う住民投票は「賛成」が「反対」を大きく上回った。
「日本の民主主義の夜明け。革命だわあ、これぇ」
(中略)
河村旋風の原動力は、市民にくすぶり続ける既成政党への「不満」や議会への「不信」だったと言っていい。停滞する国政に打開策を見いだせない既成政党、報酬削減など身を切る改革に消極的な議会―。河村は、地域政党「減税日本」という対立軸を打ち出し、既成政党や議会を「敵役」に仕立てることで民意を一手に集めた。
以上引用終わりです。
福岡でも、同じ様な流れを作れれば、と考えています。
2011年02月07日
河村市長の以前のインタビューです。

河村たかし名古屋市長のご意見が、素晴らしいです。
http://www.data-max.co.jp/2010/06/kawamura04.html
・徴収者に、納税者が反抗するのが、歴史
・マッカサーが、戦後の焼け野原で、税金で、身分保証したのがスタートで、これが、続いているのが問題。
・続けると癒着が生まれる。
・徴収者側に議会がついている。
・議会は、納税者側に立つべき。
・議会が徴収者側につくと、増税になる。
福岡市の健康保険が高いのに、福岡市議会から、追及の声が出ないのは、これで納得です(共産党のみ追及)。
自分たちの給料が、福岡市役所の予算から出ているのだから、増税側に回っているのですね。
市議会の報酬を減らして、長年続けるのが、損な仕組みに変えないと、福岡市役所と、福岡市議会の蜜月の関係は、なくなりませんね。
2011年01月11日
「改革姿勢は本物か」西日本新聞の連載

「改革姿勢は本物か」【ようこそ県議会へFKG84】西日本新聞の連載の連載の第5回です。今回で終わりです。
以下、内容を抜粋します。
福岡県議会は、全体の4割が無投票、うち5選挙区は、4年連続無投票でした。無投票となった選挙区数は、統一地方選で行われた全国44道府県議選の中でも最多だった。
県議会が定数と選挙区割りの見直しへ動いたのは改選から3年後の昨年だった。協議の場は、非公開の代表者会議。選挙区は1減、定数は2減の86となった。
県議会は昨年末から、政務調査費の使途基準の厳格化、海外視察制度の廃止など、次々と「改革」策を打ち出している。ただ、その理由は「マスコミや県民の批判が大きいから」議員たちが何か問題を把握し、自発的に見直したとは言い難い。
以上、抜粋終わりです。
選挙区や定数の問題が、非公開なのは、とんでもないです。住民の声を聴いいたり、報告会を開くなどの「議会基本条例」の早期の制定が望まれます。
今回の西日本新聞の連載記事の担当者は、川原田健雄、郷達也、前田絵さんだそうです。お疲れさまでした。「FKG84」というネーミングといい、よい連載だったと思います。
2011年01月10日
【議会基本条例の制定】1月3日の西日本新聞

【議会基本条例の制定(各自治体の実情に合わせて、住民本位の議会に)】
1月3日付けの西日本新聞より、引用します。
議会基本条例とは議会運営の理念や原則を定めた条例。06年に北海道栗山町議会が全国で初めて制定した。町民参加を促すための議会運営や情報公開の徹底、町民に対する議会報告の定例化などを想定している。
記事によると、1月3日現在、福岡県では、大牟田市、久留米市、田川市、八女市、豊前市、小郡市、春日市、宗像市で制定されています。以上までが、引用です。
残念ながら、福岡市では、制定の動きが見られません。平成23年4月の統一地方選挙に向けての政治活動は、活発になってきていましたが、このような議会の改革に関する公約や政策の提案を、現職市会議員や立候補予定者のHPなどで、ほとんど確認できません。
議会基本条例は、自治体によって、名称や内容は異なるので、作っただけで、名前だけの場合もある可能性もあります。行政主導で、住民参加が不十分な例もあると思います。住民たちの議論の中で、精査しながら、住民のための条例を作ることが大事であると考えています。
ぜひ、福岡市でも、平成23年4月の統一地方選挙までに、住民との対話の中で、議会基本条例の制定を、公約として掲げる立候補者が、多数出てくることを望みます。
参考文献:地方議会改革マニュフェスト(日本経済新聞)
http://www.amazon.co.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88-%E6%97%A5%E7%B5%8C%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB/dp/4532490731
2011年01月08日
「ようこそ県議会へFKG84」西日本新聞

昨日まで、1面で、「首長VS議会」の連載があっていましたが、福岡版(29面)で、福岡県議会の連載をしていました。
今日で、4回目で、政務調査費の問題を、取り上げています。
今までの内容も、かなり県議会に対して批判的なことが書かれており、西日本新聞の地方議会に対する真摯な取り組みに、敬意を表したいと思います。
今日の西日本新聞で、政務調査費を実費清算してはどうか、という提案がありました。
私も、その通りだと思います。



